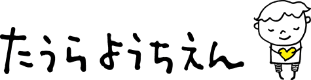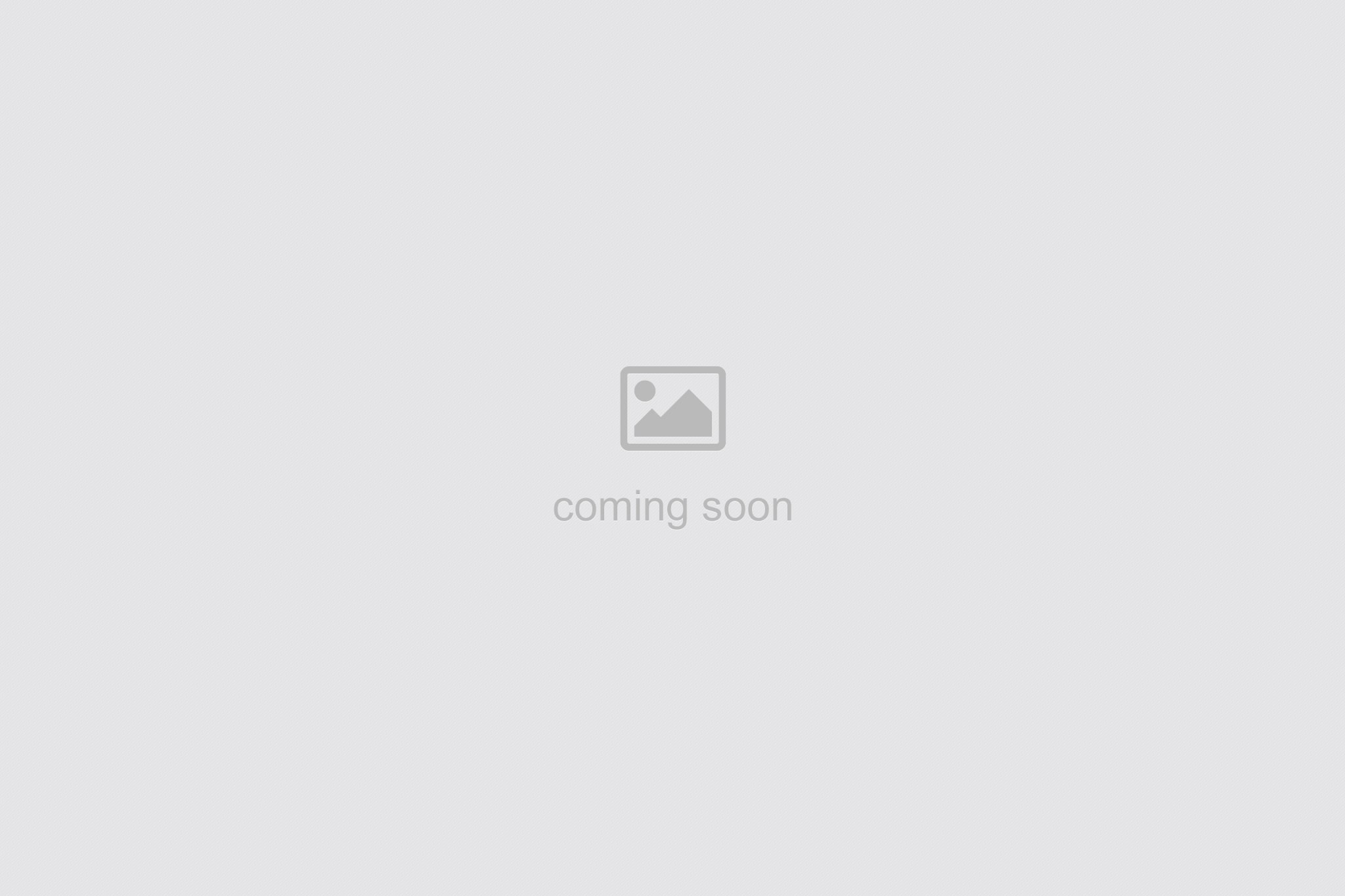ブログ
Q.141 お稽古事の選び方
2024-07-18
Q.お稽古事の選び方のアドバイスをお願いします
A.まず、お子さまがやりたがったお稽古がよいと思います。次に、親御様が大きな負担にならないお稽古を探されてみてはいかがでしょうか?
【好きこそ物の上手なれ】
惹かれるものがあるから、好きなのだと思います。好きなことは長続きします。才能のあるなしにかかわらず、続けていると実力がつきます。努力の積み重ねの上に成果を出す喜びの体験は、生涯の財産です。だから、お子さまがやりたがったお稽古が、基本的にはよいと思います。
【体作りをしてから、やった方が良いスポーツもある】
全身運動や体感を基礎作りして、ある一定の年齢になってから、始めた方が良いスポーツもあるそうですから、よく情報収集をしましょう。早くから始めればよいというわけでもないようです。
【絶対音感は就学前に】
絶対音感がつくのは、幼少期といわれていますので、音楽のレッスンは、幼児期から始めて大丈夫だと思います。
【親の経済的負担】
身長が伸びる毎に、買い換えが必要なお稽古事はあります。また、発表会や試合毎に服や靴、スポーツ用品を購入するお稽古事がありますので、経済的負担も考慮しましょう。
【親の肉体的負担】
お稽古事の送迎をするのは親です。サッカーや野球などは、送迎だけでなく、親同士でお手伝いをする事が考えられます。試合があれば、家族総出で応援に行くこともあるので、帰宅後の洗濯や食事を誰がどうするのか、考えることも必要かと思います。
【親の時間管理力】
兄弟姉妹が同じ曜日に保護者送迎が必要な別々のお稽古事がある。あるいは、上のお子さまは塾がある一方で、下のお子さまはお稽古事がある場合も考えられます。保護者さまの時間管理も重要です。
【場の雰囲気との相性】
水泳や野球などは、お稽古中に親御様が待っている事があると思います。保護者さまが待機している場の雰囲気が、お家の方と相性がよければ、長く続けることが可能だと思います。
【親しき仲にも礼儀あり】
お稽古事が楽しくて、おふざけが高揚したり、おしゃべりに夢中になったりすると、本来のお稽古の目的からずれてしまうことがあります。先生やコーチに教えてもらう立場なので、素直に聞き、時間を守り、挨拶をすることが、『最低限のマナー』であると伝えたいものです。
Q.140 子どもによい音楽は?
2024-06-24
Q.『胎教用の音楽』の話は聞いたことがありますが、『幼児用のよい音楽』はありますか?
A. 『胎教用の音楽』は幼児期も『心の穏やかさ』の点で、有効です。
【身近な人の心の状態】
お仕事をしているとき、同僚や上司が、いつもイライラしていたり、怒りっぽかったり、落ち着きがないと、自分までそわそわしたり、気持がざわついてきます。ざわついた心の状態は、周りの人に悪影響を及ぼしてしまいます。
【心の穏やかさ】
『わが子には、人から好かれる人になってもらいたい。』と思うのは親心です。人柄が穏やかであることは、一緒に過ごす人にとっては、とても重要です。その為、仏教には座禅があり、平静心の大切さをお釈迦様は説かれたのだと思います。
【α波と穏やかさ】
穏やかな状態の時の、その人の発信している周波数はα波だと言われています。α波は、周波数でいうと8Hzから13Hzの範囲で、落ち着いている状態の時に出る周波数だそうです。
【胎教用音楽はα波の音楽】
胎教用音楽はα波の音楽で、ヒーリング効果が高いと言われています。集中力の向上にも使われることがあります。ですから、胎教用音楽は赤ちゃん限定音楽ではなく、幼児にも大人にも有効な音楽だと思います。
【α波の音楽】
α波の音楽の種類は、クラシックの中から、胎教用の音楽をネット検索されると出てくると思います。又、鳥の声や水の音等自然界の音を収録した物もα波の音として、癒やしや心に潤いを与えてくれています。
【童謡】
昔ながらの童謡は、高低の音の差に無理がなく、リズムも複雑でなく、言葉もきれいな言葉と使っているので、幼児用として聞かせて、一緒に歌うと、楽しいと思います。
【近年の子どもの歌】
メロディーも、リズムも、言葉も、時代にマッチしていますので、基本的にはお子さまは喜ぶと思います。幼児は歌から言葉を習得する事がありますので、親御様が使わせたくない言葉の歌詞があるようなら、その曲は聞かせなくてよいと思います。
【BGMで流れる言葉】
親御様が聞きたい曲を、家でも車の中でもBGMとしてお使いになると思いますが、注意点はあります。まず言葉です。子どもに聞かせたくない言葉を使っていたら、子どもが幼稚園に行っている間に聞いた方が良いと思います。
【コマーシャルで使われる音楽】
コマーシャルで使われる音楽は、一瞬で情報をチャッチしてもらう目的があるので、基本的にメロディーもリズムも刺激的です。この種類ばかりずっと聞いていると、お子さまは活発化してきて、場合によっては落ち着きがなくなるかもしれませんので、聞かせすぎにご用心ください。
【現代音楽の特徴1】
一昔の歌謡曲や古典的なクラッシックは、○○長調○○短調といった『調が始めから終わりまで一定』又は『調が1回転調しその後元の調に戻る』程度でした。テレビやYouTubeから流れている現代の音楽は、めまぐるしく変わります。
【現代音楽の特徴2】
『○分の○拍子』も1曲の中でめまぐるしく変わっています。刺激は強いので、お子さまの場合は、落ち着く音楽を聴かせて、睡眠につくなどの配慮は必要かなと思っています。
【田浦幼稚園内の音楽】
元気いっぱいに童謡を歌い、ダンスをし、遊び回るお子さま達ですので、BGMは基本的にα波の音楽です。園内の音楽を割合で言いますと、童謡やダンスの音楽3に対して、流しっぱなしのα波のBGMは7程度だと思います。
以上、ご家庭教育の参考になれば幸いです。
Q.139 夫婦喧嘩をしない方法はありますか?
2024-05-23
Q.子育てで喧嘩をしてしまいます。喧嘩をしない方法はありますか?
意見の相違は、ご夫婦の育ってきた『それぞれの家庭文化や教育の違い』が、子育てという具体化によって、表面化してきているのだと思います。『互いの育ちを理解しようとする』ところから始めてみては、いかがでしょうか?重要なのは子どもの前で喧嘩をしないことだと思います。
【ズバリ喧嘩をしない方法】
喧嘩しない方法は、『互いに喧嘩をしない』と取り決めをして、互いに約束を守れば、喧嘩しないで済むと思います。無理なら、相手を理解する方法や、仲直りの方法を工夫されることをお勧めします。
【お釈迦さまの教え:自分を変えることはできるが、相手を変えることはできない】
人類普遍の法則を説かれたお釈迦様は、『自分の心や考えは自分の意志で100%変えることができるけれども、相手をコントロールすることはできない』と、説かれています。その為、相手を理解しようとする事から、始めることをお勧めします。
【自分の親の影響は、自分の子育てに影響を与えていると言われています】
一般的に、ご本人が意識しているしていないにかかわらず、自分を育ててくれた父親の影響は、自分の息子の子育てに影響を与えると言われています。自分を育ててくれた母親の影響は、自分の娘の子育てに影響を与えていると言われています。
【理解することは愛することと同じ】
理解することは愛することと同じと言われます。伴侶の育ちを理解する方法として、伴侶の実家に行ったときに、家族関係を見たり、子ども時代のことを聞いてみると、家庭文化や子育て方法はわかると思います。その他に、伴侶の御両親の口癖はなんだったか、聞いてみるのも、伴侶を理解する基になると思います。
【仲直り方法】
田浦幼稚園の先生方に、夫婦喧嘩の仲直り方法を聞いてみましたが、ご夫婦のタイプによって、仲直り方法は違うようです。『・自分の言い分は必ず言っておく。・その日のうちに解決し、次回同じような事が起きた時の教訓にする。・その日のうちに何とかしようとすると険悪になるので、ひとまず寝て、朝起きてからどうするか考える。等がありました。』
【重要:子どもの前で喧嘩をしない】
未熟で欠点がある同士がひとつ屋根の下で暮らしているのですから、意見の相違は当然あります。喧嘩をするなら、子どもがいない所や寝てからされることをおすすめします。父母のいさかいは、お子さまの心に暗い影を落としますので、お互いに気をつけましょう。
【夫婦調和の工夫】
子育ては、自分達夫婦がそれぞれどのように育てられたか、色濃く影響していますので、互いの育ちを理解し合ったり、考えを話し合ったりして、ご自分達夫婦を中心とする家庭の文化を新たにどう作っていくのか、夫婦調和の工夫をクリエイトされることをお勧めします。
Q.138 行きしぶりの対応
2024-05-17
Q.私の子どもは休みのたびに行きしぶりがあります。心配でたまりません。どうしたらよいでしょうか?
A.幼稚園の玄関やバス停で、親子の話し合いをするより、あっさり離れた方が、よいこともあります。そしてプラス思考で自己肯定感をじっくり育みましょう。
【人の目が気になるかもしれませんが…】
幼稚園の玄関や、バス停で泣かれると、先生や周りの人の目が気になりがちです。良いお母さんであろうとすると、疲れてしまいます。その為、人の目は脇に置いといて、その場でお子さまと、真正面から向き合って見てはいかがでしょうか?ママが向き合ってくれたとお子さまご自身が思うと、ママから離れるエネルギーになっている様子です。
【お金のかかる取引はしない方が良いと思います】
『帰りに○○を買ってあげるから、幼稚園に行きなさい。』等は、一度成功体験を身につけてしまうと、小中高生になって成長するたびに、ゲームやスマホ、お金など、交渉内容が増額される可能性があります。その為、物質的な取引はしない方が良いと思います。
【家族の愛情が伝わるお楽しみなら大丈夫です】
『お家に帰ってから、公園に遊びに行こう』とか、『お迎えに行ったときにハグしよう』とか、『元気に幼稚園に行ったことをパパにおはなしして、喜んでもらおう』など、家族の愛情が伝わるお楽しみといった、精神的喜びなら大丈夫だと思います。
【登園後の親子の以心伝心】
ママと幼児は、以心伝心で気持ちが伝わっています。幼稚園にいるわが子を心配していると、お子さま自身の気持の切り替えがなかなかできないこともあります。登園後は、お母さま自身が携帯電話の電源を切るように、お子さま以外のことに気持を向ける事も大切かと思います。
【何で幼稚園に行くのが嫌なの?】
『何で幼稚園に行くのが嫌なの?』と帰宅後に聞いてみるのは大切かもしれません。但し、ぐずるたびに聞くと、理由をなんとか考え、本当の理由でないことを言うこともありますので、毎回聞かなくてもよいのではないかと思います。ただ『お母さんと離れるのが寂しいだけ』かもしれません。
【幼稚園で嫌なことなかった?】
帰宅後、『幼稚園で嫌なことなかった?』とマイナス部分を毎回聞いていると、お子さまは、マイナスを言うとママの関心が自分に向けられると感じて、マイナスを探すようになります。人のマイナス部分を繰り返し見つけていると、周りは自分を害する存在として見えてきて、お子さまが体調不良を起こしたり、不安が増すなど、負のスパイラルに入ってしまうことがあります。
【いいところ探し】
反対に、お友達の素晴らしさや楽しかったことを、毎回話していると、プラスのスパイラルに入りますから、心身共に明るく元気に過ごしているお子さまが多いと感じています。
【心配と取り越し苦労】
お子さまを常に心配することが、親の愛だと思っていませんか?自分の不安を、とりあえず全部お子さまに言ってしまっても、ママの不安は満たされず、ママの心配は増大します。必要な心配と不必要な心配の仕分けを理性的にしてみましょう。不必要な心配を『取り越し苦労』と仏教的には言います。
【失敗からしか学べない知恵があります】
『お母さんが言ってくれなかった』と幼児期は言いがちです。何でも先回りして、教えておいてあげることが親の愛ではありません。幼児期に小さな失敗をさせておいてあげると、立ち直り方や創意工夫する力がついてきます。失敗からしか学べない知恵があることを知識としてご活用下さい。
【心配性のお子さまには自己肯定感を】
幼稚園で今日は新たに何をするのかわからなくて、泣くお子さまもいます。その場合は、『今日はこんな新しいことがある』と予告してあげましょう。一方で、お子さまの関心事を見つけて、伸ばし、自己肯定感をつけてあげると心配性が薄れてくると思います。
【自己肯定感の育みは時間が必要です】
自己肯定感の育みは、時間がかかります。親の努力だけでは難しい場合は、幼稚園やお稽古事の先生の力をご利用下さい。お子さまが生まれてきたときに、天から授かった素晴らしさが、輝くことを願っています。
Q.137 水道の蛇口が旧式なのはなぜ?
2024-04-25
Q.水道の蛇口が旧式のひねるタイプなのはなぜでしょうか?
A.自分から行動を起こす能動的点でも、手首や指先の動作があるという点でも、お子さまの脳細胞の発達に良い刺激を与えると思っています。
【便利さの中に潜む注意点】
センサーで、照明がついたりお水が出たりする時代で便利ですが、お子さまの成長にとって、本当にそれで良いのか、立ち止まって考えてみるのも良いのかもしれません。何でも相手にしてもらう受動型よりも、自分から行動を起こす方が、能動的マインドを育むことができるのではないかと思います。
【能動マインドと脳の刺激】
幼児期の脳細胞は、善い刺激によって、大きく成長すると言われています。その為、自分から行動する積極的な姿勢は、とても大切だと思います。指先の作業も、脳の刺激にとてもよいと言われています。その為、幼稚園の水道の蛇口は旧式の自分でひねるタイプです。
【水加減の調節が難しい】
右に回すか左に回すか、わからなくなることがあり、水が止められないことがあります。
水の出口を上に向けて噴水のようになって、床が水浸しになることもあります。水の調整加減は、失敗の経験から学んでいきます。
【冬場は水の冷たさに泣くことも】
夏場は水道の蛇口をひねることができたとしても、冬場は冷たくて泣いてしまい、蛇口が触れない満3歳のお子さまもいます。家庭内で冬場は手洗いの水が温水なのかなと思いました。年少組になると、幼稚園では冬場でも水道の蛇口に触ることができています。
【蛇口を閉めることで区切りをつける】
ご家庭では、水道水が自動的に止まるシステムかもしれませんが、幼稚園では蛇口を閉めなければいけません。これが面倒で、トイレのお後、手洗いをしないで出ることもあるので、定期的に、手洗いをするよう伝えています。水を自ら止めることは、自らの行動を終了することや、気持に区切りをつけることにつながると思っています。