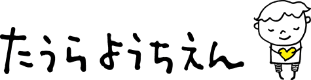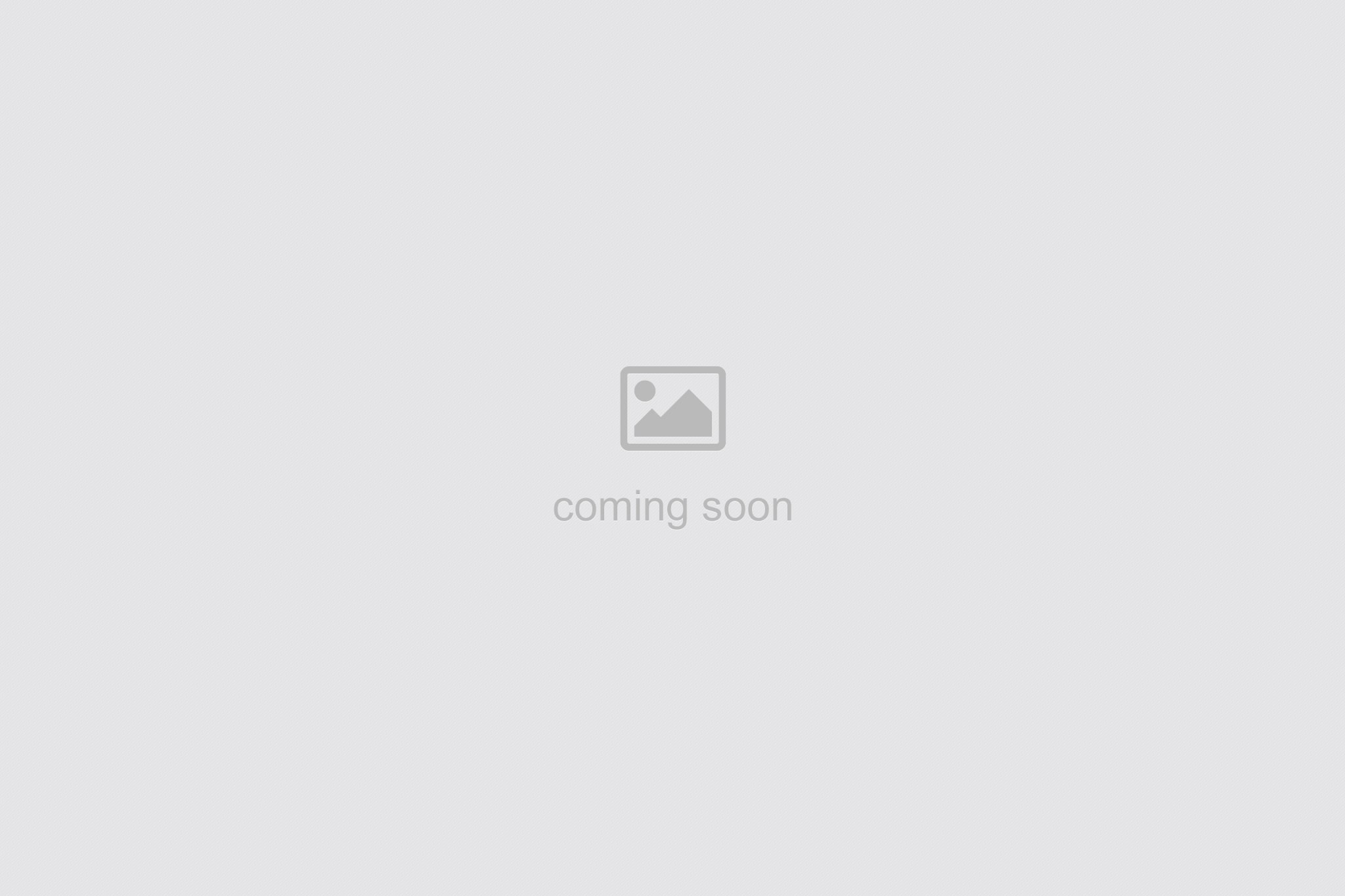ブログ
Q.82優しい子に育てるコツ
2023-03-28
Q.他人に優しい子どもに育てたいのですが、どのように子育てをしたらよいでしょうか?
A.優しい子に育つ為に必要なことは、最低2つあると思います。まずご家庭で、色々な方々に生かされている感謝を常々語ることが、優しい子に育つ原点だと思います。2つ目は、幼児期は、優しいお友だちの集団の中で、優しさとは何かを五感で感じ取り、実践し、幸福感を実感していくことが大切だと思います。
素敵なご質問をしてくださり、ありがとうございます。
【優しい子に育てるコツ1:生かされていることの感謝を語る。】
2歳3歳の頃は、自分が地球の中心にいるように思い込む時期があります。
大人の言葉の理解は出来ない時期かもしれませんが、大人が大事なことを話しているらしいと感じる感性は、どのお子さまにもあります。
ですから、育てる側が、『電気を発明してくれた人のお陰で、夜も絵本が読めてありがたいね。』『自分達はお米を作ることは出来ないけれど、田んぼで育ててくれた農家の人にありがとうだね。』『一生懸命働いてくれるお父さんにありがとうだね』等、感謝の気持ちを、しみじみ語ることで、お子さまの純真な五感を刺激することは出来ます。
【感謝が人に対する優しさに変わる瞬間が訪れます。】
3歳4歳頃になると、お家の方の口癖をまねるようになりますから、言葉だけでなく、真心を込めた感謝の大切さ伝えると、心からの感謝の言葉が出てくるようになります。
心からの感謝の言葉を続けていると、感謝が人に対する優しさに変わる瞬間が訪れます。その一瞬を捉えて家族が喜ぶと、いいことなんだなあと、家族の反応でわかる様子です。
【ほめられるために優しくするのが初めの一歩】
3歳4歳頃は、大人の反応が嬉しいので、ほめられたくて優しくします。これは自然の摂理なので、悪いことではないと思います。『○○してあげたよ』と報告することもあります。
このような経験の中で、善悪の善をお子さまは学んでいます。 ですが、ここで優しさの子育てを終了してしまうと、大人になっても、『優しくしたのにお礼をしてくれなかった。』とお返しを求める人になりがちです。
例えば、ボランティア活動をしても、お返しを求め恩を売るようになっては、真のボランティアになりませんので、この次の段階が肝心なのです。
【子どもが感謝しなくても優しくしてくれるお母さんの存在】
自分達がどれだけ多くの人に生かされているかを、お子さまと発見し、語り合うことはとても大事だと思います。
幼稚園では、『お母さんは赤ちゃんの時に、どれだけミルクを飲ませてくれたか回数を聞いたことはありますか?
生まれてから今まで何回オムツを替えてくれたか聞いたことはありますか?みなさんがありがとうを言わなくても、オムツを替えてくれましたね。
お母さんは具合が悪くても、幼稚園の帰りのバスを待っていてくれましたね。
頑張っているお母さんにありがとうを言いましたか?』等、身近なお母さんのことをたとえて、見返りを求めない優しさとは何かを伝えています。
そして、お母さんだからやってくれて当たり前と思うのではなく、感謝の気持ちが大切だと伝えています。
ご家庭であれば、お子さまのご両親、兄姉、祖父母などを話題にされてもよいかと思います。
【お返しがなくても優しく出来る人に】
『たとえ自分が他人に1個優しくしても、その10個分20個分100個分、わたし達は人々に優しくされています。
だから、お母さんのようにお礼を言われなくても、ほめられなくても、優しくしていきましょうね。
みんなにお友だちでいてくれてありがとう、家族でいてくれてありがとうの気持で、優しくしていきましょうね。』と、子ども達に、純粋な優しい心の実践を、わたし達は促しています。
【ほめられるための優しさと、お返しを求めない思いやる気持から出た優しさは質において全く違うと思います。】
【優しい子に育てるコツ2:集団の中で本当の優しさを感じ取り、実践し、優しくすることの嬉しさを実感する】
【お兄さんお姉さんから優しくされる体験】
入園すると、お兄さんお姉さんが優しくしてくれます。
みなさまこの世に生まれて数年の純真な時期ですから、以心伝心で、お兄さんの姉さんの純粋な優しさは、小さなお友だちの純真なハートに伝わっていく様子です。
【自分が成長し、年下のお友だちに優しくする体験】
自分がお兄さんお姉さんになると、当たり前のように、年下のお友だちに優しくしていきます。
優しくされた体験があるので、どうやったら優しく出来るのか実践できる様子です。
【同年齢からの学び】
家の中では、大人がお子さまに合わせてくれますが、同年齢同士だと、遠慮がありませんので、そのつもりはなかったのに、相手を泣かせてしまったり、競争心から悔しい思いをしたりする事があります。
どのようなことをすると相手を悲しませるのか、どのようにしたら嬉しい思いになってもらえるのか、悔しいときや苦しいときにどのように立ち直るのか、等を体験から学んでいきます。
【自分が人にされて嬉しいことをするのが優しさ。】
わたし達は、『自分が人にしてもらったら嬉しいなあと思うことを、人にすることが優しさです。』と伝えています。
お友だちが悲しんでいるときや悔しがっている時に、自分の悲しさ悔しさの体験があると、言葉のかけ方が無機質でなく、真心からの言葉のかけ方になります。
そして相手を思いやる心が、相手に伝わっていきます。
【悲しさや悔しさがあるからこそ、更に優しい人になることが出来るようになる。】
優しさは悲しみや悔しさの中からも生まれます。
悲しさ悔しさの実感があるからこそ、心の襞(ひだ)が細やかになります。そして、真心からの優しさが生まれてきます。
そこには、見返りを求めたり、恩を売るような気持や、優しさの自己アピールの気持はありません。
【子ども達は集団生活の中で学んだ、真心からの優しさの行為をしたときの幸福感を、心の宝物にしていきます。】
わたし達は、『優しくしてあげる言動』ではなく、『生かされている感謝を他の人にお返ししていく気持や、見返りなしの真心込めた言動』を優しさとして、大切に育んでいます。