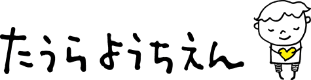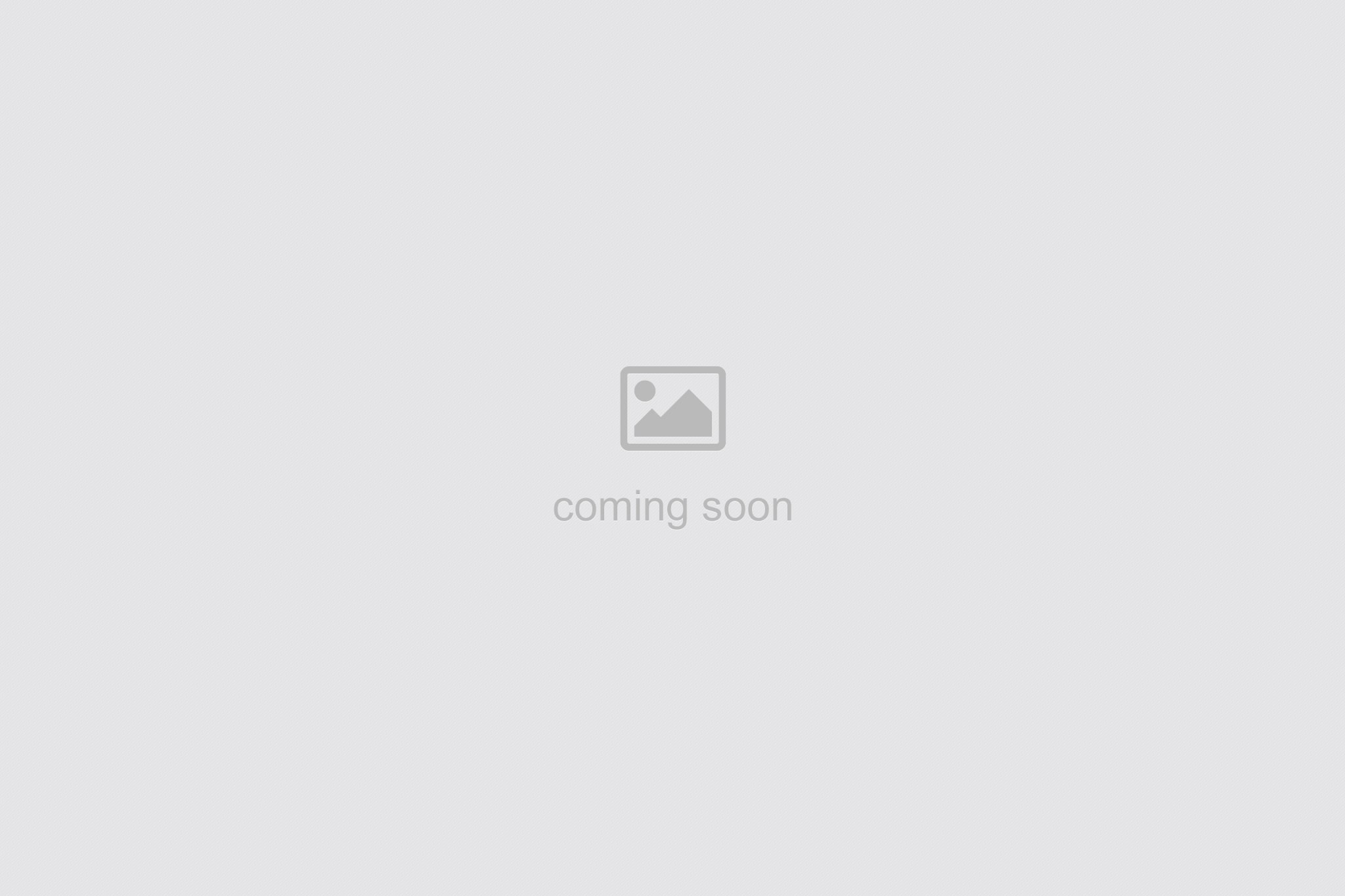ブログ
Q.154 幼稚園とこども園保育園との違い
2025-04-13
Q.田浦幼稚園とこども園保育園は、どこが違うのでしょうか?
A.幼稚園は教育の場で、学校教育のスタート地点となります。保育園は福祉の場です。こども園は教育と福祉の両方が要素として入っています。
【教育の場が幼稚園】
田浦幼稚園のように、私学助成の幼稚園は、文部科学省の管轄です。文部科学省は、幼稚園は学校教育のスタート地点と位置づけしています。幼稚園は教育の場です。福祉的要素は少ないです。
こども園、保育園はこども家庭庁の管轄です。私学助成の幼稚園と比較して、こども園そして保育園の順に、福祉的的要素が大きくなります。特に保育園は、お世話をしている時間が長いのが特徴です。
【田浦幼稚園の教育の前提にあるもの】
田浦幼稚園がお子さまを教育するにあたり、前提としているのは、仏教精神と、幼稚園教育要領に基づいた教育であることです。
【教育と福祉の違いから見えてくる田浦幼稚園の特色その1『善悪』】
仏様の教えに基づいた集団での教育ですので、2歳児から年長組まで、善悪の基準は全員同じです。お子さま個々人には、色々なハンディーや育ちの違い、得意不得意の違いはありますので、全く考慮しないわけではありません。しかしながら、原則正しさの基準は、仏様の教えからの正しさです。人としてどのように生きるかの基本は、全員同じです。
こども園や保育園など、福祉的要素が加わる施設の場合、色々なハンディーや育ちの違い、生まれ持った特質に応じて、福祉的な対応が考えられます。その為、善悪の物差しは全員同じとは限らず、田浦幼稚園と比較すると、善悪がゆるやかな可能性があります。
【教育と福祉の違いから見えてくる田浦幼稚園の特色その2『預かり保育』】
田浦幼稚園は、介護をしていても、こどもを何人育てていても、お仕事をしていても、母親という立場は、 全員一緒です。つまり、預かり保育を利用されるとき、保護者さまのご事情を考慮して、優先的にお預かりの予約ができるわけではありません。2号認定のお子さまの優先はございません。
こども園や保育園は、福祉的要素がありますので、保護者さまのご事情に応じての預かり保育となっている様子です。
【教育と福祉の違いから見えてくる田浦幼稚園の特色3『保護者さまの行事参加』】
特色2でお伝えしたように、母親という立場は全員一緒なので、幼稚園の保護者さまの行事参加は、ほぼ全員参加です。なぜなら、お子さまの成長を保護者さまと幼稚園と二人三脚で育む上で、必要と思われる行事だからです。年間予定は、年度の初めにお知らせしています。参加される方は、御両親でなくても成人のご家族のどなかで大丈夫です。
こども園や保育園は、福祉的要素がありますので、家庭のご事情に応じての対応が考えられます。
以上簡単ではございますが、私学助成の田浦幼稚園と、こども園保育園との違いをお伝えさせて頂きました。
Q.153 親として勉強になったこと
2025-03-22
オススメ
Q.田浦幼稚園に入れて親として勉強になったこと
A.『こどもの話を、よく聞くようになった。』というご意見は多く、親子の会話が増えた様子です。
令和6年度、卒園児保護者さまの気づきをご紹介します。
♡気が長くなったと思います。
♡こどもが、相手のよい点に目を向けてくれるので、私自身が怒ることや『なんで!?キー』といってばかりいたのが、新しい発見や素直に感謝する気持ちを伝えられるようになりました。
♡日々、時間に追われて「~しなさい」と自分の意見を押しつけることが多かったのですが、少しずつこどもの話を聞くことができるようになりました。こどもも話を聞いてもらえると嬉しいようで、色々話してくれるようになりました。
♡こどもが一生懸命何かをやっているときは、たとえ時間がかかっても『待つ』ということが少しはできるようになったと思います。
♡3人目ということもあるので、自分にも少し余裕があり、上2人の時と比べ、本人のチャレンジを止めることなく、見守ってあげられるようになりました。
♡集団生活の中で、感じることなど、本人が困ったり悩んだりを聞くことで、改めて人間関係について、一緒に考えるようになりました。
♡初めての子育てて、少し細かく神経質になったところがあったと思いますが、いい意味で、気楽になれたと思っています。
♡同じ自分の子でも、兄弟姉妹で全く違う人間なのだなと実感し、それぞれの子に合った言い方や教え方をしていかなくてはいけないと気づけた事は、私の成長なのかなと感じています。
♡『仏様はいつも見ているよ』とこどもから教わり、こどもの個性を認めてあげる事や、親の欲求を押しつけない事で、親も心おだやかに成長できたと感じます。
♡小さいながらも幼稚園で沢山学んで、こんなにもしっかり考えられるのだと気づくことが多かったです。『まだ小さいから』ではなく、まずこどもの話にしっかり耳を傾けていきたいと思いました。
『保護者さまの気づきは、わたし達教員にとっても宝物です。こども達の話に耳を傾けることができるよう、心おだやかな、自分達でいる努力をしていこうと、改めて思いました。ありがとうございました。』
Q.152『お友だちパパ』のメリットデメリット
2025-02-11
Q.わが子と対等に接する『お友だちのようなパパ』の良い点と注意点を教えて下さい。
A.『お友だちパパ』のメリットは、父子の心が通い合うことだと思います。注意点は、お子さまが、目上の人との関係学を、家庭内で実体験できるよう育むことだと思います。
【お友だちパパのメリット】
パパ自身がこども心に戻って、わが子の好奇心の向く分野に共感することは、お子さまにとっては、自分のことをわかってくれる人が家庭に居るということですので、とても心強いと思います。父子の絆が生まれると思います。
【メリット:わが子の興味や関心事は何か】
わが子の興味や関心事は何か見つけましょう。乗り物や昆虫、地図、自然の不思議に関心のあるお子さまは多いです。きらきら光る物に興味があったり、物語に夢中になったり、色彩の世界に没頭したり、スポーツに夢中になるお子さまもいます。
【メリット:こどもの好奇心を開拓する】
自分は不得意であったとしても、わが子が興味関心があるのでしたら、その分野に自分もこども心に戻って、没頭してみて下さい。例えば自分はカナヅチだったとしても、わが子がすいすい泳ぐ様子を見て、魂の躍動感を共有することは可能です。
【メリット:父子の絆】
幼少時に、父子の心の絆が育まれると、小学校に就学してお友だち関係に意識が向くようになっても、お子さまが相談したいことがあった時に、話しかけてくれる可能性があります。お友だちパパは、話しかけやすいパパだと思います。
【メリット:こどもが話しかけたとき】
こどもがお友だちパパに話しかけるタイミングは、パパが運転中の時か、一緒に遊んでいる時か、パソコンに向かって仕事をしている最中か、疲れてくたくたなときか、わかりません。「後でね」と返事をしたら、24時間以内に、耳を傾けるようにしましょう。約束の実行は、信頼につながります。数日経つと、「もういい」と言われてしまう可能性があります。
【お友だちパパの注意点】
「1年365日お友だちパパであること」はお勧めしません。家庭は社会の縮図です。目上の人との関係学を学ぶのは、社会に出てからではなく、幼いながらも、父親との関係から、家庭内で実体験します。言葉の理解はできなくても、肌感覚で本能的に学習しています。
【叱れない上司のデメリットとの共通点】
ハラスメントの問題があるので、なかなか叱れない社会になりつつあります。しかしながら、部下や後輩に注意しないと、組織体の仕事そのものにダメージが出たり、組織全体の倫理観が低下する場面があると思います。お仕事も子育ても、人を育てることに違いはありません。お友だちパパは、仕事に於いて、必要に応じて部下に注意ができない上司になってないか点検してみましょう。
【上司と部下も、親と子も魂の尊さは同等】
上司と部下も、親と子も、仏様のこどもですから、魂の尊さに於いては同等です。しかし、経験知は全く違います。先に生まれてきた人が、後から生まれてきた人に知恵を伝えるのは、あたりまえのことです。
【お友だちパパの注意点:世界標準の善悪】
経験知を伝える上での基準は善悪です。『これをされたら嬉しいか嫌か』ゴールデンルールと言われる物差しです。国や民族や文化の違いはあっても、人類は同じように感じるように神仏が創って下さったようで、世界標準の基準です。
【お友だちパパの注意点:善悪を曖昧にしない】
曖昧な言い方や、その日によってパパの善悪の物差しが微妙に変わったら、お子さまは、善悪は身につきません。何がいいことで、何が悪いことなのか、具体的にわかりやすくが大事です。そしてお子さまにわかりやすいように、言葉や、動作や、絵や写真などの工夫は必要です。
【お友だちパパの注意点:乳幼児期の最低限のマナーの育み】
善悪の前に、食事の食べ方や、触ってよい物いけない物等、最低限のマナーを伝えたくても、言葉が理解できないので無理だと考える方もいらっしゃると思います。愛着関係ができている場合ですが、お子さまは、パパの本気度が本能的に感じ取ることができます。(ママの本気度は更に敏感に感じ取ります。)
【お友だちパパの注意点:内心嫌われる事を恐れていないか】
内心『わが子に嫌われませんように』と思って、お子さまに最低限のマナーを伝えると、言っていることはわからなくても、パパの何かわからない恐怖心だけは受け取ります。小学生くらいになると、『パパは建前ではいいことを言ってるけれど、本音では自分が好かれたい事が最優先で、優先順位の次がわが子なんだな』と見抜くお子さまもいます。
【お友だちパパの注意点:お子さまを優先順位一位で教え育む】
父親の役割の1つは、母親との協力関係で、わが子を社会に有用な人材として、成人する頃までに世の中に送り出すことです。言葉の理解はまだ難しくても、『幸せになってくれ』と真心を込めた願いで、最低限のマナーを忍耐強く伝えていけば、『パパは自分の事を思って言ってくれている』ことは、確実に伝わります。だから、『パパの嫌がることはやめよう』という気持になります。
【お友だちパパの注意点:最低限のマナーや善悪を全く教えなかったら】
最低限のマナーや善悪を全く教えなかったら、幼稚園では友達関係でつまづきがちです。理由は、お友だちパパは自分に合わせてくれますが、同年代のお友だち全員が、自分に会わせてくれることはまずないからです。学校ではまず先生との関係で、仕事を始めると、上司との関係でつまずきがちです。教え導く人の意見に素直に聞く耳が、幼少期に育成されなかったことが原因の1つと思われます。
【父親の厳しさを見せる一面は必要】
子育ての9割は寛容であってよろしいと思いますが、「パパが駄目と行ったら駄目」という一面は、こどもが成人するまで、精神的大黒柱として必要だと思います。どうか「パパなんて大嫌い」と言われることを恐れないで下さい。母親だって言われることがありますが、こどもの一言で家事や育児をやめてしまう母親はいません。「パパ嫌い」と言われてへこんだり、カッと怒る必要はありません。気分で言っているだけで、本心はパパに愛されたいのですから、理性的にその言葉は水に流しましょう。
【お友だちパパの注意点:親の一言の重み】
人として生きていく上で必要なことは、誰かがわが子に教えてくれるのではありません。御両親のお役目です。なぜなら、愛着をもった御両親の言動は、幼いお子さまの魂に深くしみこんでいくからです。保育者が100回言ってお子さまに通じないことでも、親の一言の影響力は大きいです。私は、日々実感しています。
【身近な誰かが教えてくれていた】
食事のマナーとか、よそのおうちにおじゃましたときのマナーは、自分は覚えていなくても、近しい人が教えてくれていないと、今の自分はいないはずです。動物的な本能ではなく、人として生きることができるよう、人類は連綿と親から子へと伝えてきています。
【最低限のマナーは、愛着関係を持った人から、学ばないとできない】
まだ小さいからとか、言ってもわからないからと放任してたら、身にはつきません。また、ママ任せにして、パパが放任でこどもの好きにさせていても、身につきません。両親そろって、同じように導くことは大切です。
【お友だちパパの注意点:導き方】
『やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、ほめてやらねば人は動かじ(山本五十六の言葉)』です。子育ても、部下の育て方も、相手は人ですから基本は同じです。カッとして怒鳴ったら、お子さまも部下もは『怒り』を受けとります。知恵の伝達にはなりません。注意すべき言動を理性で伝えつつ、相手の長所や人格を愛する気持が大切だと、常々感じています。
【お友だちパパの注意点:忍耐】
サポートや育みには、忍耐が大事です。3歳くらいになったら、頭ごなしではなく、同じ事をされたら自分は嬉しいか、考えを聞くことも大切です。何度でもできるまで、繰り返しが必要です。なぜなら、お子さまは記憶したことをすぐ忘れるからです。動物はすぐに大人になりますが、人間は約20年かかります。神仏は、子育ての中での喜びや苦悩の中で、親自身の人格成長を期待されているのだと思います。
【子育ての中で、自分の器を広げる】
子育ては平坦な道ではありません。山あり谷ありの子育ての中で、会社での人材育成につながるような発見があるはずです。あるいは、会社で培った、自分の忍耐力や包容力を、子育てに生かすこともできるはずです。田浦幼稚園は、パパの人生や人格に磨きがかかる子育て経験を応援しています。
【結論】
お友だちパパの良さは、『こども心に戻って、わが子の好奇心を開拓することで絆を深めることができること』だと思います。お友だちパパの注意点は、『親も子も魂の尊さは同等。しかし経験知に違いがあるので、パパは人としての生き方を導く、こどもの人生で最初の人なのだと自覚しましょう』ということだと思います。
【補足1-1こどもと接触が少ないパパへ】
お仕事の関係で、ほとんどお子さまとの時間が取れないパパがいらっしゃると思います。そのような場合は、お子さまが成人するまで、言い続けていただきたい、魔法のような言葉があります。『ママを悲しませたり、困らせてはいけないよ♡』です。
【補足1-2魔法の言葉の2つの意味】
『ママを悲しませたり、困らせてはいけないよ』の意味の1つは、『パパがママを、とても大切に思っている』というメッセージが、お子さまに伝わります。意味の2つ目は、自分がこの言動をしたら、お母さんが悲しんだり困ったりするかどうかは、どのお子さまも年齢を問わずわかります。お子さまにとって、わかりやすい善悪の判断基準の言葉だと思います。
【補足1-3魔法の言葉を使うのは原則パパです 】
『ママを悲しませたり、困らせてはいけないよ』をママ自身が言うと、『ママのためのこどもの人生』と、お子さまが勘違いする可能性があるので、ママはご自分で使わない方がよろしいかと思います。『パパを悲しませたり、困らせてはいけないよ』 をママが言う場合は、ママがパパをとても尊敬していたり、父子関係が強い絆で結ばれている場合は、効果があるかもしれません。
【補足2:1人親の方へ】
ママが1人でお子さまを育てている場合、パパの代わりをしてくれる、おじいちゃまや親戚のおじさまがいると、ママは助かると思います。小中高の学生だと、お稽古ごとの先生や、スポーツクラブのコーチが、父親代わりのようなご指導をして下さることがあります。ママが父親役も兼任するのは、心身共にきついのではないかと思いますので、参考にされて下さい。
Q.151 teracoとは?
2024-12-16
Q.teraco cafe のteracoとはどういう意味でしょうか?
A.寺子とは、『仏様の子ども』という意味です。
【仏性(ぶっしょう)】
どの方も、神仏から『善なる固有の輝き』を授かって、生まれてきています。
それを、仏様と同じ性質という意味で、『仏性(ぶっしょう)』といいます。
お家の方々も、お子さま達も、仏性が宿っています。
【仏様に愛されていることを感じる空間に】
仏様と同じ性質を宿している者同士としては、大人も子どもも、共通です。teraco cafeが、日頃の疲れを癒やし、互いの仏性を尊重しながらも、大人も子どもも、お一人お一人が、仏様に愛されていることを感じ取る、『なごみの空間』になることを願っています。
Q150.子どもが言うことを聞かないときに
2024-11-28
Q.子どもが言うを聞かないときに、どうしたらよいでしょうか?
A.『お子さまの個性や年齢に応じて』になる思います、
【もので釣る方法】
お菓子やおもちゃなどの「物を買ってあげるから」や、やったらケーキ屋さん等「お店に行こう」では、年齢と共に費用がかさむ可能性があることと、いつか通用しなくなる時が来るかもしれません。
【ママの不在を予告する方法】
お出かけで、気に入った場所から離れないとき、「置いてくよ。ママいくから。」と言うと、あわててついてきてくれるお子さまは良いのですが、我関せずのタイプの方もいる様子です。
【気持を聞く方法】
『何が嫌なの?』と、とことん理由を聞いてあげる方法もあります。言葉で自分の気持ちが説明できたり、大人が気持ちをくんであげたりできる場合は、有効かもしれません。
【選ばせる方法】
「どちらがいい?」と2者選択方法は、お子さま自身が自分で選ぶので、嫌々させられている感は少ない可能性があります。
【予め約束する方法】
買い物の時は、予め現地到着前に、買う物を全部言って、これ以外は買わないと約束する方法もあります。あるいは『1コだけ、どのコーナーでお菓子を選んだら良い』と約束する方法もあります。
【カウントする方法】
・1から始めてカウントする。「今日は○秒でできたね。」とほめる。
・5からカウントダウンする。0までに終了しようとするので、幼稚園では、わりと有効です。
【ママの顔色で察する】
ママの雰囲気とか様子を見て、察するようにしていく方法があります。
【ママのマインドを変える】
「絶対これをしなければいけない。」のママのマイルールを変えると、ママは精神的に楽になる場合があります。
【もので釣る方法】
お菓子やおもちゃなどの「物を買ってあげるから」や、やったらケーキ屋さん等「お店に行こう」では、年齢と共に費用がかさむ可能性があることと、いつか通用しなくなる時が来るかもしれません。
【ママの不在を予告する方法】
お出かけで、気に入った場所から離れないとき、「置いてくよ。ママいくから。」と言うと、あわててついてきてくれるお子さまは良いのですが、我関せずのタイプの方もいる様子です。
【気持を聞く方法】
『何が嫌なの?』と、とことん理由を聞いてあげる方法もあります。言葉で自分の気持ちが説明できたり、大人が気持ちをくんであげたりできる場合は、有効かもしれません。
【選ばせる方法】
「どちらがいい?」と2者選択方法は、お子さま自身が自分で選ぶので、嫌々させられている感は少ない可能性があります。
【予め約束する方法】
買い物の時は、予め現地到着前に、買う物を全部言って、これ以外は買わないと約束する方法もあります。あるいは『1コだけ、どのコーナーでお菓子を選んだら良い』と約束する方法もあります。
【カウントする方法】
・1から始めてカウントする。「今日は○秒でできたね。」とほめる。
・5からカウントダウンする。0までに終了しようとするので、幼稚園では、わりと有効です。
【ママの顔色で察する】
ママの雰囲気とか様子を見て、察するようにしていく方法があります。
【ママのマインドを変える】
「絶対これをしなければいけない。」のママのマイルールを変えると、ママは精神的に楽になる場合があります。